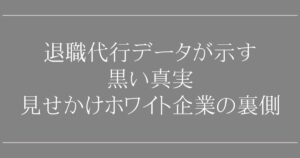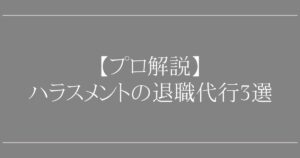「退職代行を使っただけなのに、会社から『損害賠償を請求する』と連絡が来た…」
「上司から『お前のせいで大損害だ!』と脅されて、どうしていいかわからない」
「円満に辞めるために退職代行を頼んだのに、なぜ私が悪者に…?」
もしあなたが今、退職代行を使ったことで会社から不当な請求や脅しを受け、恐怖と不安でいっぱいなら、この記事を読んでください。
あなたは何も悪くありません。そして、泣き寝入りする必要も全くありません。
この記事では、数多くのお客様の退職をサポートしてきた専門家の視点から、会社からの理不尽な「被害者ヅラ」に屈せず、逆に会社の責任を追及するための具体的な法的手段を解説します。
- なぜ会社は、退職したあなたを「加害者」に仕立て上げるのか?
- 損害賠償を請求された時に、絶対にやってはいけないNG行動
- 無料で相談できる「労働基準監督署」の賢い使い方
- 弁護士に相談し、不当な請求をはねのけ、逆襲する方法
この記事を読み終える頃には、あなたは不当な請求への恐怖から解放され、自身の正当な権利を守るための冷静な知識と具体的な行動プランを手にしているはずです。
退職代行は被害者?会社の理不尽な主張3パターン
会社は、なぜ退職したあなたを攻撃してくるのでしょうか。
それは、労働者の正当な権利である「退職」を認められず、感情的になっているケースがほとんどです。
まずは、会社が主張してくる典型的な言い分と、それが法的にいかに的外れであるかを知り、冷静さを取り戻しましょう。
「突然辞めて損害が出た!」という主張
これは最も多い言い分です。
「お前が辞めたせいでプロジェクトが止まった」「代わりの人間を雇う費用を払え」などと主張してきます。
しかし、そもそも労働者には「退職の自由」が憲法で保障されています。
民法上も、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、会社の合意なく退職は成立します。
一人の社員が辞めたことで業務が回らなくなるのは、労働者個人の責任ではなく、会社の体制(マネジメント)の問題です。
これをもって損害賠償を請求することは、原則として認められません。
繁忙期に辞めたい場合でも、労働者の権利は守られます。
詳しくは、こちらの記事も参考にしてください。
リベンジ退職を繁忙期に決行!【退職代行が解説】トラブルを100%回避する3つの秘策
「引き継ぎが不十分だ!」という主張
「まともな引き継ぎもせず、無責任だ」と、責任感を煽ってくるのも常套手段です。
確かに、労働者には信義則上の引き継ぎ義務があるとされています。
しかし、退職代行業者は、必要な引き継ぎ資料の提出(郵送など)についても、適切に会社へ伝達するのが一般的です。
あなたが貸与物の返却や最低限の引き継ぎに応じているにもかかわらず、会社が「不十分だ」と主張するのは、単なる嫌がらせである可能性が高いです。
そもそも出社を拒否せざるを得ないような職場環境を作ったのは会社側であり、対面での引き継ぎができない責任をあなたに押し付けるのは筋違いです。
引き継ぎの法的な義務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
リベンジ退職で引き継ぎ無視はOK?【退職代行のプロが回答】法的に問題なく辞める方法
「訴訟も辞さない!」という脅し
「弁護士に相談した」「裁判を起こす準備をしている」などと、法的な措置をちらつかせて、あなたを精神的に追い詰めようとします。

安心してください。これは99%、単なる「脅し」です。
実際に、退職した個人相手に会社が訴訟を起こすには、莫大な費用と時間がかかります。会社にとって、メリットはほとんどありません。
本当に訴訟を起こすつもりなら、感情的な電話ではなく、弁護士を通じて「内容証明郵便」が届くはずです。
もし書面が届いた場合は無視せず、すぐに対応が必要ですが、口頭での脅しに屈する必要は全くありません。
万が一、会社から警告書などが届いた場合の対処法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
リベンジ退職で法的措置を通告された!【弁護士が解説】警告書・損害賠償の全知識
被害を訴えられた時の相談先|泣き寝入りしないための3つの法的手段
会社の主張が不当だとわかっても、一人で戦うのは不安ですよね。
ここからは、あなたの強い味方になってくれる相談先と、具体的な法的手段について解説します。
行動を起こす前に、まずは利用した退職代行業者へすぐに連絡し、状況を共有することを忘れないでください。
労働基準監督署への相談|会社の違法性を追及する
「会社を辞める原因が、そもそも会社側にあった」という場合に非常に有効な手段です。
労働基準監督署(労基署)は、会社が労働法規を守っているかを監督する行政機関。
相談は無料で、匿名でも可能です。
こんな時は、労基署へ相談!
- 未払いの残業代がある
- 給料の支払いが遅れている、または支払われていない
- 上司からのパワハラやセクハラが横行していた
- 有給休暇を消化させてもらえなかった
- 長時間労働が常態化していた
労基署に相談し、会社に労働基準法違反の事実が認められると、労基署は会社に対して調査や是正勧告を行います。
これは、会社にとって非常に強力な圧力となります。
会社からの損害賠償請求に対して、「そもそも御社には、このような法令違反がありましたよね?」という強力な反論材料(カウンター)を手に入れることができるのです。
ただし、労基署は損害賠償請求のような民事トラブルには直接介入できません。
あくまで、会社の違法性を公的に指摘させるための「カード」と考えるのが賢い使い方です。
労働局のあっせん|話し合いでの解決を目指す
裁判まではしたくないけれど、当事者同士では話がまとまらない。
そんな時に利用できるのが、労働局の「紛争調整委員会によるあっせん」という制度です。
弁護士や大学教授など、労働問題の専門家である「あっせん委員」が、あなたと会社の間に入り、中立的な立場で話し合いを仲介してくれます。
あっせん制度のメリット
- 手続きは無料で、非公開で行われる
- 裁判に比べて、手続きが簡単で迅速に解決できる可能性がある
会社からの不当な請求を取り下げてもらうための、交渉の場として活用できる制度です。
弁護士への相談|最強の代理人で逆襲する
会社からの請求が執拗である場合や、法的な措置を本気でちらつかせてきた場合、最終的かつ最も強力な手段が「弁護士への相談」です。
弁護士は、あなたの完全な味方(代理人)として、法的な観点からあなたを完璧に守ってくれます。
私が代理人になれば、今後の会社とのやり取りは全て私が行います。
あなたはもう、会社と直接話す必要は一切ありません。精神的な負担はゼロになりますよ。
弁護士ができることは、防御だけではありません。
労基署への相談内容(未払い賃金やハラスメントの事実)をもとに、会社に対して慰謝料や未払い賃金の支払いを求める「逆請求」をすることも可能です。
ここで、私が担当したお客様の話をさせてください。
20代のCさんは、退職代行サービスを利用してデザイン会社を退職しました。
すると翌日から、元上司から「お前がプロジェクトの途中で投げ出したせいで、クライアントから契約を切られた!損害額は300万円だ!すぐに払え!」と、脅迫まがいの電話が毎日のようにかかってくるようになったのです。
精神的に追い詰められたCさんは、利用した退職代行業者に相談。
業者が提携する弁護士を紹介してくれました。
相談を受けた弁護士は、まずCさんを安心させ、すぐに行動を開始。
弁護士の名前で、元上司と会社宛に「不当な請求であり、これ以上本人へ直接連絡する行為はストーカー規制法や脅迫罪に問われる可能性がある」という内容証明郵便を送付しました。
すると、ピタリと連絡は止まりました。
話はここで終わりません。弁護士がCさんの勤務状況を詳しくヒアリングしたところ、恒常的な長時間労働と、デザイン料が支払われていないサービス残業が発覚。
弁護士が未払い残業代を計算したところ、その額は100万円を超えていました。
弁護士はすぐさま、会社に対して未払い残業代の支払いを請求。
立場は完全に逆転し、最終的に会社側がCさんへ解決金を支払う形で和解が成立しました。
Cさんは、「被害者だと思って怯えていたのに、弁護士さんのおかげで逆にお金を取り返すことができ、本当にスッキリしました。勇気を出して相談して良かったです」と、笑顔で語ってくれました。
Cさんのように、「被害者」だと思っていたあなたが、実は「請求する権利を持つ側」であるケースは非常に多いのです。
弁護士と提携している退職代行サービスなら、このような万が一のトラブルにもスムーズに対応できます。
裁判沙汰や損害賠償トラブルに巻き込まれたくないなら、専門家を頼るのが一番の近道です。
- リベンジ退職で損害賠償を請求された!【弁護士が解説】訴訟を回避できる退職代行3選
- リベンジ退職で裁判沙汰に?【弁護士監修】法的トラブルに強い退職代行サービス4選
- リベンジ退職【パワハラ】が原因なら|弁護士が教える!慰謝料も請求できる退職代行
まとめ|正しい知識と専門家を味方に、不当な請求と戦う
今回は、退職代行を使った後に会社から「被害者だ」と主張された場合の、具体的な対処法について解説しました。
会社からの損害賠償請求や脅しは、そのほとんどが法的根拠のない、感情的な嫌がらせです。
しかし、一人で立ち向かうのは困難です。
そんな時は、
- まず、利用した退職代行業者に相談する
- 会社の違法性を追及するために、労働基準監督署を賢く利用する
- そして、あなたの最強の代理人となる弁護士に相談する
という手順を思い出してください。
あなたは、会社の不当な主張に屈する必要は全くありません。 正しい知識を身につけ、専門家を味方につければ、あなたの正当な権利は必ず守られます。
泣き寝入りという選択肢はありません。
冷静に、そして毅然と対応し、新たな人生への一歩を安心して踏み出しましょう。